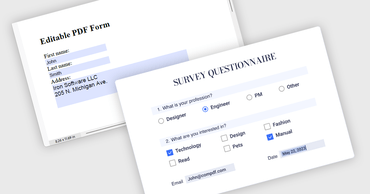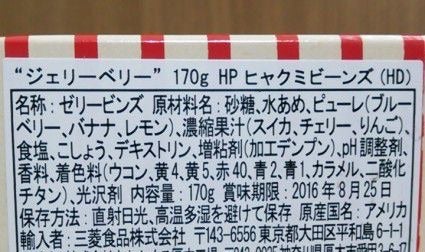彼女は彼を愛していた。彼も、彼女を愛していた。ふたりの関係は、とても素晴らしいものだった。このままいつまでもつづけばいいと、ふたりとも思っていた。
だが、丸2年つづいて3年目目に入ってすぐに、ふたりは別れなくてはいけないことになった。
ふたりの関係は、ほんとうに素晴らしいものだったが、未来にむかって発展的に拡大していけるような関係ではなかった。未来などなにもあてにできないし約束もできない関係だったのだ。いまのこの関係という枠組みの内部だけで完璧に自己完結してしまって、それ以上にはどう考えたって広がっていきようのない関係だった。
ふたりにとっては、しかし、それだけで充分だった。ほかにはなにもいらない、とにかくいまの関係がこのままのかたちでいっまでもつづけばよかった。
いつかは終わりが来て別れなくてはいけなくなるにちがいないと、ふたりとも思ってはいた。思ってはいるけれども、彼女のほうにも、そして彼のほうにも、自ら進んでいまの自分たちの関係を終わりにしたいと思ったりするようなことは、まったくなかった。
別れのための直接的なきっかけは、誰にとっても等しい量で加算されていく時間というやつが、もたらした。
彼女と彼の関係は、彼女が23歳のときに、はじまった。彼との関係が2年つづき、彼女は25歳になった。結婚、ということに関する話題は、彼女の周囲に、いつもいくらでもあった。彼女自身の身の上にも、20歳になる以前から、縁談が持ちこまれたりお見合いの話が舞いこんだりして、結婚は常になんらかのかたちで、うっすらとではあるが、影を落としていた。
やがて自分も結婚するのだろうなあ、というごくあいまいな予感はあったけれども、結婚に関する彼女の認識はその程度にとどまり、20歳をすぎても、21歳になっても、そして22になっても、結婚が具体的なかたちをとって彼女の目の前に立ちはだかることは、ついぞなかった。
そして、23歳になって、彼と知りあった。素晴らしい関係が、はじまった。彼との結婚はまず考えることはできないが、そんなことなどまったく考える必要のないほどに、関係それ自体がじつに素晴らしく、このままいつまでもつづけばそれだけで自分は充分に幸せだと、彼女は確信するようになっていった。
彼との関係が2年つづいて彼女は25歳になった。そして、ある日のこと、一天にわかにかき曇って起こってくる雨嵐のように、結婚ということが、彼女の行く手に立ちはだかった。
彼女の実家は関西にあるのだが、その地方でのたいへんな名家なのだ。親を中心に、親類だのなんだのが十重二十重に名家というものの伝統をとりまいていて、いったんその内部にとりこまれたなら、にっちもさっちもいきはしない。彼女自身、そのことは、よく知っていた。それがいやさに、学校も東京の学校を選び、名家の伝統がおよばないところで自由な生活を楽しんできた。
自分の行く手にいきなり立ちはだかった結婚は、彼女の親が彼女のためにすべて用意をととのえ、きわめて強引に、しかしごく当然のことのように、彼女に押しつけようとしている結婚だった。
はじめのうち、彼女は、抵抗するつもりでいた。強引な押しつけに対して、たたかうつもりでいた。
東京から関西の実家へ何度も帰っては、親がおぜんだてした結婚に対する抵抗を、展開した。
だが、たたかえばたたかうほど、そして抵抗すればするほど、実家というもののなかにおける、長女としての自分の位置およびその位置が持たなくてはいけない独特な機能のようなものが、はっきりと見えてきた。
そういったものがよく見えていないうちはとにかく抵抗してたたかっていればそれでよかったのだが、よくわかってくると、彼女の気持ちは微妙に変化してきた。
複雑な問題がいろんなふうにからみ合っているそのまんなかに自分がいる。その自分が親の言うとおりすんなりと結婚して所定の位置と機能を持ってしまえば、すべての問題は解決する。
ということがわかってくるにしたがって、彼女の心は、ぐらついてきた。親のすすめる強引な結婚に賛成するわけではないのだが、いっぽうで気持ちはゆらぐのだ。
自分ひとり首をたてに振りさえすればいいのだと思うと、自分の気持ちのなかにそんなものがあるとはこれまで一度も思ってみなかった古風な正義感のようなものが、頭をもたげてくる。
お見合いとそれにつづく結婚をもうちょっとで承知しかかる自分をなんとかおさえ、週末ごとに帰っていた実家から、彼女は東京へもどってきた。
名神、そして東名をひとりで車を走らせつつ、彼女は考えに考えた。
東京にある自分の部屋へ帰りついたころには、結論が出ていた。彼女は、部屋から実家へ電話をした。電話に出た母親に、彼女はお見合いをします、と伝えた。
彼に言うべきか、言わずにおくべきか、大いに迷った。そして、彼にはなにも言わないまま、彼女は、親のおぜん立てによるお見合いをした。
彼女はいろんな意味で非常に魅力のある女性だから、お見合いの結果は、もちろん成功だった。ぜひとも、と相手方からは乞われ、彼女のほうも、相手に対しては好印象を持った。相手に関しては、ととのいすぎるほどにととのった条件がそろっている。
お見合いは、成立した。結婚式にいたるまでの、名家どうしの複雑な段どりが、あっというまにきまっていった。
東京に帰った彼女は、お見合いが成立したことを、涙ながらに彼に伝えた。
彼は、動揺していた。悲しみもした。だが、最後は彼女の決意を、気持ちよく祝福してくれた。そうすることがもっとものぞましいし、そうするよりほかにないからだ。
東京の生活をひきはらって関西へ帰るぎりぎりの日まで、彼女は、東京にいた。いよいよ今日でおしまいという日、彼と会った。国道沿いのドライヴ・インで、秋晴れの週末の午後、ふたりは会った。彼女は自分の自動車でドライヴ・インへいき、彼も自動車で来た。
コーヒーを飲んで、それでお別れするつもりだったのだが、二台の車で夕方から夜、夜どおし、そして夜明けまで、いっしょに走ることになってしまった。
2台の車が、おたがいに前になったりうしろになったりして、とにかく、西へむかった。夜ふけのコーヒーをドライヴ・インで飲んだり、夜明けの近い時間に海を見おろす国道の展望台に立ったりした。
そして、ついに、夜が明けた。国道のわきにならんで車をとめ、最後の口づけをかわし、それぞれの自動車に乗りこんだ。
彼の車が、さきを走っていく。夜明けの、西へむかう国道を、彼女の車が、あとからついていく。
1時間ちかくそうやって走りつづけてから、国道の分岐点に出た。ここが別れだ、とはっきりわかるような分岐点だった。彼の車はすこしスピードをあげ、分岐点を右へ曲がっていく。西へむかう彼女は、反対に左折しなければならない。
左のウインカーをつけてハンドルを左へきるという行為が、このときほどつらかったことはないと、彼女は、そのときからすでに数年をへたいま、美しく微笑しつつ、言っている。
(底本:エッセイコレクション『「彼女」はグッドデザイン』1996年)